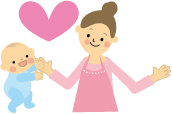子育てQ&A
7. 性格の問題
落ち着きがない →閉じる
子どもは、いつも活発に動き回っているのが普通で、大人から見れば、元気な子は常に落着きがありません。心配した方がよいのは3才を過ぎても興味が次々と移り、1つのものに集中して遊べない場合です。このような時には、小さい時に1人遊びをたっぷりさせたか、1人遊びをしている時に余計なかかわりをして遊びを中断させることが多くなかったか、振り返ってみなければなりません。
3才を過ぎても、どんな遊びにもあまり関心を示さず、友達や大人の周囲にいることが多い場合は、児童相談所などに相談してみましょう。
こわがり →閉じる
こわがりの子は想像力が豊かであったり、危険が予測できたりという能力の豊かな賢い子が多いのです。「こわくないよ」「こわがりだねえ」などとなじるのでなく、「そうだねえ」「心配なんだね」と気持ちを受け止めてあげましょう。こわくてトイレへ行けないような子には、手をつないで一緒に行くことでスキンシップにもなり、そのうち行けるようになります。
赤ちゃんの人見知りや、お母さんの後追いをするのは正常な発達をとげている証拠です。
人見知り →閉じる
赤ちゃんが3〜4カ月頃になると、いつも世話をしてくれる人以外の人が近づくと、泣いたり、顔をそむけたりします。人見知りをすることは、いつも世話をしてくれる人をしっかり覚え、その人が大好きになったということです。子どもはまず誰かに(大抵は母親)愛着を覚えることで育っていきます。むしろ人見知りをしない子が心配なのです。人見知りをしている子でも、だんだん危害を加えない人だということが分かってきて、沢山の人に安心して笑顔を見せてくれるようになります。
やる気がない →閉じる
子どもは正常に育っていれば、何事にも好奇心いっぱいで、新しいことにどんどん挑戦していきます。子どもがやる気を出さない原因は、◆大人の過保護・過干渉のため、要求が子どもから出る前に手を出している
◆いつも否定されていて、自分に自信がない
◆かわいがられたり、受け入れてもらっていない
◆体調が悪い
◆能力よりあまりに高い課題でやる気がおこらない
などです。子どもが失敗するのは当り前です。失敗を許し、やろうとした意欲を大いに認めていくようにすれば少しづつやる気が出て来ます。
自閉的傾向 →閉じる
3、4才になっても極端に1つのことにこだわって、周囲の言うことを受け入れられない場合や、言われたことに対し、うまく言葉のキャッチボールができなかったり、おうむ返しが多かったり、自分の言いたいことを一方的に話し続けるだけであったりする場合は、自閉的傾向を疑ってみなければいけません。集団の中での子どもの様子をよく観察し、専門機関へ相談しましょう。
母から離れられない →閉じる
赤ちゃんがお母さんから離れられないのは当然のことで、正常な発達です。少しづつ周囲のことに興味を持つようになり、離れられるようになります。たとえ、朝、泣いてお母さんと別れても、すぐに泣き止んで、保育園では楽しく遊び、お母さんがお迎えに来ると、飛びついていくということになります。
いくつになってもお母さんから離れない子は、下の子が生まれたり十分にだっこしてもらっていない場合などが考えられます。
お家でうんとかわいがられ、たっぷりだっこしてもらっている子は、集団の中にも早く元気に入っていけるようになります。
人をかむ →閉じる
6、7カ月の頃の赤ちゃんは歯の生え始めの時期で、確かめるために、お母さんの手や腕にかみつくということがよくあります。自我の芽生える2才頃の集団の中では、かみつきが多くなります。おもちゃの取り合い、保育士の膝の取り合い、時には特に理由もないのに目の前にいたというだけでかみついてしまうこともあります。
かんだ時には、その都度、「貸してって言おうね」「ごめんって言おうね」と声をかけ、友達とつながる言葉、仲良くなれる言葉を教えていきます。
そして、楽しい遊びの工夫をして、子どもたちのイライラの解消に努め、噛む状況を作らないようにしていきます。
また、家庭で母親にたっぷりだっこされ、愛情をいっぱいもらっている子は、噛むということが少ないのも事実です。
人をたたく、ける →閉じる
人をたたいたり、けったりしておもしろがるような時はきちんとした関わりが必要です。「よくないことだ」ということを目を見てきちんと伝えましょう。その上で、欲求不満やストレスの発散と受け止め、抱きしめたり、スキンシップを十分にとり、じっくりと関わります。
家で上の子や父母にいじめられたり、体罰を受けている子が集団の場で、たたいたり、けったりして気持ちを発散させるということもあります。
いずれにせよ、乱暴な子は心が満たされていない状態です。周囲は愛情をたっぷりと伝える方法を探らなければなりません。