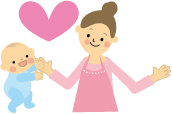子育てQ&A
5. しつけ
こづかいの与え方 →閉じる
まだお金の値打ちが分らず、計算や記録のできない幼児にお金を持たせることは避けるべきでしょう。買物の経験をさせたい場合は、親と一緒にしましょう。
小学校3年頃より、金銭教育の意味で少しのこづかいを与えてもよいでしょうが、何にいくら使ったかを記録させ、親が管理しなければいけません。そのためにこづかい帳を共に与え、点検をきちんとします。使途が不明の場合は、こづかいを与えません。
また、こづかいでどの範囲のものを買うか、親子できちんと取決めをしておきましょう。
金額は、他の家に左右されず、親と子が話合って決めましょう。お金の大切さ、お金を得るために誰が働いているかも話してあげましょう。
よく家の手伝いをさせてお金を与えるという家がありますが、「家の仕事をするのはあたりまえのことだ」という正常な感覚を失わせてしまいます。
また、小銭があちこちに転がっていて管理ができない家庭では正しい金銭感覚が育ちません。大人は子どもの手の届かないところにお金をきちんと片付け管理すべきです。
しつけのポイント →閉じる
◆食べる、寝る、遊ぶの生活のリズムを作ってあげること◆むやみにおもちゃを与えないこと
◆スキンシップを心掛け、話しをよく聞き、気持を受けとめること
◆いけないことをした時はきちんと言い聞かせること
◆挨拶をきちんとさせること。大人がお手本を示すこと
◆自分でやりたがる気持ちを大切にし、見守り、できない時にそっと手を貸すこと
◆失敗しても認め、はげまし、できるだけいろいろなことに挑戦させること
◆歯みがき、うがい、手洗いなど、清潔のしつけをすること
◆しつけとは、一度にできるものではない。大人が根気よく「しつける」ものであると認識し、あわてず、あきらめず、気長にやること
祖父母の甘やかし →閉じる
じっくりと子どもの話を聞いてくれ、無条件でかわいがってくれる祖父母の存在は本当にありがたいもの。しかし、むやみにおやつを与えたり、何でもゆるしたり、そうかと思えば、子どもが自分でやろうとしていることにも全て手を出してしまったり、とかく祖父母に育てられた子どもは、依存心が強く、意欲がなく、「三文安い」と昔からよく言われます。
家庭でも意見の食い違いから無用な対立を生むことがないよう、はじめに家族の中で話合い、子どものことで共通理解をしておきましょう。
◆むやみにおやつを与えないこと
◆むやみに金銭を与えないこと
◆むやみにおもちゃを与えないこと
◆子どもが自分の力でできることはできるだけさせること
などです。話合いをする時は、「本に載っていた」「保育園にこう言われた」など、とよその人の意見として話題にしていくとぎくしゃくしません。
祖父母に限らず大切なことは、家族全員でその都度話合い、一貫したしつけがなされることです。
衣服の着脱 →閉じる
子どもは1才半ぐらいから何でも自分でやりたがるようになります。大人がした方が早く上手にできて当り前ですが、できるだけうまく手を貸しながら子どもに達成感と自信をもたせるようにしましょう。◆1・2才
ズボンの上げ下ろしができます。
ズボンを脱ぐのは楽ですが、上げるのは大人がお尻の方を上げて、前の方は自分でさせるようにします。大きなボタンなら止めやすいところにあるものは止めることができます。はじめは大人がボタンホールから半分出してあげ、子どもが残りをつまんでひっぱり出すようにさせます。首の近くのボタンはまだまだ難しいです。
◆2・3才
上着が着られます。
かぶって着る上着、Tシャツ、セーターなどは首だけ通してやり、手は自分で出させるようにします。前開きの上着は体の前にかませて、マントのようにパッとかぶせるようにして背中側へやり、袖を通させます。袖は始め、片方は大人がやってあげます。ズボンのうしろも声かけにより自分であげることをさせます。
◆4・5才
ボタン止め、ぬいだものをたたむことをさせます。着脱は一応の完成です、ひもを結ぶことが次の課題です。
お風呂 →閉じる
本来、入浴は楽しいものです。乳児がお風呂を嫌がるのはお風呂に落されたり、お湯が熱過ぎたり、顔にお湯がかかったりといった嫌な経験があったからかも知れません。
お風呂を嫌がったら、恐怖心を取除かれるまで、肌着のままで入れ、はじめは手と足だけ入れるようにしましょう。ベビーバスの中で洗う自信のない人は無理をせず、外にバスタオルを敷いて赤ちゃんを置いて洗いましょう。
バスにつける時は「気持ちいいね」と声をかけましょう。
幼児になっても嫌がる子は、好きなおもちゃや人形などと一緒に入ろうねと誘ったり、手ぬぐいや石けんで遊ぶなど、楽しいお風呂になるよう工夫してみましょう。
言葉づかい →閉じる
周囲のまねをしている、家でよく上の子が言っている、回りの大人の反応がおもしろいので使ってみる、心に不満がある。原因はいろいろでしょう。大人はさり気なく、きちんとした言葉で言い返しましょう。正しい言葉や、友達とうまくつながっていける言葉を、遊びの中で教えましょう。不満がありそうな場合は、スキンシップを多くとり、原因を考えましょう。悪い言葉でイライラを発散させている場合もあります。しつけと虐待 →閉じる
虐待に走ったあげく、子どもを死に至らしめ、親は「しつけのつもりでやった」と最近のテレビでよく言われています。しつけか虐待の違いは、自分の感情のおもむくままに爆発させているか、そうでないか、ということです。イライラして爆発しそうになったら「水を飲む」「100数える」「外へ連れ出す」などして、自分の気持ちをうまく切り換えましょう。また、何でも言い合える友達をもったり、様々な育児サークルにも顔を出し、親自信が沢山の人とのつながりの中で生活していることがとても大切です。もし虐待に走りそうになった人がいたら、いつでも保育園へ来て下さい。誰だって虐待に走りそうな時があるのです。そんな自分を恥かしいと思わず、自分を助け、はげまして下さい!保育園へ電話してくれるとうれしいです。一人で悩まないで。
叱り方 →閉じる
叱る時に「お父さんに叱られますよ」「おまわりさんが来るよ」といった叱り方は効果がありません。何故いけないか、きちんと説明しましょう。その上で「ママが悲しい」「お父さんが困る」「○○ちゃんが迷惑」など、人の気持を伝えるようにします。そうすることで、人の気持ちを思いやって自分の行動を規制していける子に育っていきます。清潔のしつけ →閉じる
大人が一緒にすることで「手を洗うと気持ちがいい」「お風呂に入るとさっぱりして気持ちがいい」「歯をみがいたらお口がさっぱりして気持ちがいい」という感覚を味わわせます。その時に「気持ちいいね」と言葉かけをしましょう。いつも不潔な中にいると「気持ちいいね」という感覚を味わうことがありません。大人がまず清潔な環境を心掛けましょう。
トイレへ行ったあとの手洗いなど、根気よく見てあげることが大切です。また爪の中やトイレのばい菌の話などもしてやり、子どもの理解力に訴えるのも効果的です。
だき癖について →閉じる
だき癖は癖というより、その子の育ちに必要な要求であると受け止めましょう。だっこをたっぷりしてもらった子は、自分が愛されているという自信にあふれています。そして人を好きになり、いろんなことに自信を持って取り組む子になります。
できるだけたっぷりとだっこしてあげましょう。そのための時間がとれる様、周囲は家事などに協力しなければなりません。たっぷりだっこされて心が満たされれば、子どもは膝をはなれて遊びに出かけます。
乳児で、いつもと様子が違い、だっこしても泣き止まない時は、腸閉塞などの急性の疾患がないか、虫さされ、湿疹などがないか、耳や鼻に異物が入ってないか、空腹でないか、のどがかわいていないかなど、よく確めましょう。
おもちゃの与え方 →閉じる
子どもにとってよいおもちゃとは、値段の高い安いではなく遊びが発展し、工夫していける余地があるものです。乳児のおもちゃは、口に入れても安全なもの、たたいたり、ゆすっても壊れにくいものを選びます。ゆれたり音の出るものがお気に入りです。立派なままごとセットより、いらないお皿、木切れ、石ころ、草などの方が何にでも見立てることができ、ずっと豊な遊びを生み出します。また、おもちゃ箱の横に材料箱を置き、あきばこ、チラシ、布やきれいな紙、ひもなど、何にでも工夫できるものを用意してあげましょう。
プラスチック製品ばかりでなく、木のおもちゃや布など違う性質をもつ物もおもちゃの中に入れてあげましょう。