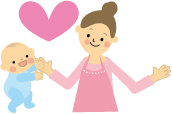子育てQ&A
4. 食事
偏食 →閉じる
幼児期になると好き嫌いがでてくるのは自然なことです。嫌がるものは無理強いせず、ほんのちょっぴりから焦らずに始めましょう。親の嫌いな食べ物は食卓にのぼることが少ないため、子どもも嫌うことが多いです。規則正しい食事時間となっているかも大切なことです。おなかがすいての食事となれば、偏食もなおるのが早くなります。
大好きなものを与える前に、嫌いなものをほんの一口食べさせてから、という方法も効果的ですが、あまりやりすぎると意地悪になってしまいます。「一口」の約束は守りましょう。意欲がなくなり、親への信頼もなくします。
少食 →閉じる
だらだらとおやつを食べつづけていないか、食事の時間は決めているか、生活のリズムをもう一度点検してみましょう。リズムが整っているのに食べる量が少ないのは本当の少食です。無理強いせずに量より質を心がけましょう。その子なりに体重が増えていて、元気なら大丈夫です。「子供は体に必要な栄養は自分から摂取する」と考え、ゆったり構え、心楽しく食べることを第一にしましょう。少食だからといって遊び食いを許したり、スプーンを持って親が追いかけることはしないほうがよいです。おやつ →閉じる
幼児は成長期ですから、おやつは必ず必要です。胃の容量も小さく、一度にたくさんの量を食べることができないからです。10時、3時をメドに与えるようにします。量は次の食事に支障のない程度にします。果物や乳製品はとてもよいおやつですから必ず与えたいものです。楽しみのため甘いものも適度に与えてもいいでしょう。離乳食を嫌う →閉じる
離乳食を始める前に、果汁やスープ、番茶など、ミルク以外の味になれさせることを十分にしましょう。また、これらを哺乳びんからスプーンへと移行させながら飲ませ、スプーンになれさせておくことが大切です。はじめは離乳食の量より、なれることが大切です。ゆっくりあせらずに、1さじからはじめましょう。はじめダメなものでも、2・3日後にはすっとお口をあけてくれることもあります。楽しみに待ちましょう。箸がうまく使えない →閉じる
箸を使う前に、スプーンは正しく持てていますか?いきなりお箸ではうまくいきません。スプーンは、始め上からの握り持ち、次に下からの支え持ち、この二つの持ち方がちゃんとできれば箸の準備OKです。まず、お箸は大人が正しい持ち方をしてお手本を示しましょう。手を添えて、正しい持ち方を教えましょう。まちがった持ち方はそっと直してあげましょう。1回の食事で、1・2回だけ直してあげましょう。あまりしつこくするとお箸を持つことが嫌になります。こぼしても叱らずに、楽しい雰囲気の中で食べるようにしましょう。はじめはすべり止めのついた箸を使うと、うまくつかむことができ、意欲を持たせることができます。
スプーンがうまく使えない →閉じる
スプーンの大きさ、握りやすさ、深さは大丈夫でしょうか?あまりに浅すぎるスプーンでは、やっとすくってもすぐに落ちてしまい、お口にもあまり入らず、意欲をなくしてしまいます。大きすぎるものは口にうまく入りません。はじめはこぼすのがあたりまえです。それどころか右手にスプーンを持ち、左手でつまんで食べるような食べ方をよくします。スプーンが飾りにすぎない時期がしばらく続きますが、赤ちゃんの手に大人の手を添え、一緒にすくって口に運んであげることも取り入れながらやってみましょう。一人で口にもっていった時は、少しでもお口にはいったらほめてあげましょう。
手づかみ →閉じる
スプーンが上手に持てるようになるまでは手づかみで食べ物を食べることが多くなります。汚いなどと言わず、たくさんさせましょう。指の5本の機能が未分化なため、はじめは5本の指で一緒に握るようにしていますが、だんだん親指と人さし指でつまめるようになってきます。手づかみを十分させた子はスプーンも早く上手に使えるようになります。お母さんが食べさせてあげるのと合わせて充分させてあげて下さい。食べ物の感触を手で確かめることで食べ物への興味、食べることへの意欲も育っていきます。離乳のすすめ方 →閉じる
4ケ月頃になって、首が座り、スプーンで果汁や番茶がいやがらずに飲めるようになったら開始です。はじめは2回目の授乳の時に、10時ごろミルクを飲む前に、野菜スープ1さじから始め、5さじ程度飲めるようになったら、どろどろのおかゆ、ゆでた卵黄、野菜のすりつぶしたものなどをいずれも1さじから始めます。味つけはしない方がよいです。7ケ月ごろから、2回食にします。夕食の時間、あるいは朝にします。舌でつぶせる固さのものを加えます。とうふ、白身魚、バナナなど食品の数も多くします。味つけはしないほうがよいです。
9ケ月頃から3回食にします。朝・昼・晩に食べさせます。まだ食後のミルクは必要です。やわらかい御飯や煮物、肉団子など手づかみにしやすい形にして与えます。味つけはうす味に。
12〜15ケ月 もう離乳は完了です。しっかり離乳食を食べているなら、もう食後のミルクはいりません。10時・3時のおやつの時に、だんだんコップでフォローアップミルクや牛乳を与えるようにします。食品は歯ぐきでつぶせる固さのものを与え、味つけは大人の味つけでかまいません。
過食 →閉じる
赤ちゃんが要求してくるのであれば、離乳食は目安を上回っても大丈夫です。ただし、よく食べるからといって、甘いお菓子類をたくさんあたえることはやめましょう。成長するにつれて好き嫌いがはっきりしてくるため、食欲は落ちるのが普通です。また同時に活発に動き回れるようになれば消費エネルギーが増えてスマートになっていきます。学童になってからの過食は他に原因があることが考えられます。ストレスをためていないか、よく話を聞いて対応しなければいけません。
断乳 →閉じる
1才ごろになると、栄養素の大部分をミルクや母乳以外の食品からとれるようになります。また、ミルク、母乳に頼っていては、必要な栄養素が十分とれなくなります。ですから1才半までにはやめさせたいものです。母乳はやめる、ミルクはフォローアップあるいは牛乳に切りかえ、コップで飲ませるようにします。スキンシップのために寝る前に母乳を欲しがる子が多いのですが、だっこやなでなでなど、別のスキンシップにかえていきます。遊び食べ・むら食い →閉じる
遊び食べがはじまったら「もうごちそうさましようね」と片付け始めます。この時ほしがるなら、もう一度だけ食べさせます。ほしがらなければ片づけます。だらだら遊びながら30分以上も食事に時間をかけることはやめましょう。意欲や集中力のない子になってしまいます。子供の食欲にむらがあるのはあたりまえです。おもちゃをかたづけたりテレビを消して、食事に集中しやすい環境をまず作りましょう。大人がまずおいしそうに食べてみせて誘いましょう。それでも食べない時は決して無理強いはせず、次の食事まで待ちましょう。食べなかったからと言って、20分ほどしてまた食べさせるような、だらだらとした食事はさせないようにします。
子どもが食べ物をこぼすのは仕方がないことです。いっしょうけんめい食べていてこぼす時は、汚しても叱らないようにします。汚したりこぼしたりすることを遊びにしてしまった時は、「ごちそうさま」させます。
かまない・飲み込めない →閉じる
子どもに歯がはえ、充分かめるようになっているのに、いつまでもどろどろのものを与えていませんか?すこしづつ歯ごたえのあるものを食べさせ、「かみかみしようね」と声をかけ、大人がやってみせましょう。飲みこめないのは、逆に、固すぎたり切り方が大きすぎて十分にかみ砕いたり歯や歯ぐきですりつぶしたりできないことが多いです。また、飲み込めないからといってお茶やおつゆなどで流しこませることはよくありません。声をかけ、十分に「かみかみ」させましょう。汁物は汁物として与えるようにしましょう。