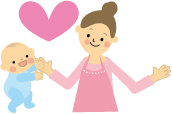子育てQ&A
14. 問題行動
目をパチパチする →閉じる
病気でもないのに、幼児が目をパチパチさせたり、咳をしたり、肩を上げ下げしたりするのはチックの一種です。チックとは、体の一部がくり返し動いてしまうことを言います。注意するとよけいひどくなります。
チックで気持ちを落ち着かせようとしているのです。ゆったりとした気持ちで包みこみ、チックにはふれないようにしまよう。心が育つにつれ、ひとりでになおっていきます。
人見知り →閉じる
8ヶ月ごろから始まる人見知りは、知能の発達してきた証拠です。やがて、見知らぬ人も自分に危害を加えることがないと分ってくると、だんだん人見知りはなくなってきます。2才ごろには、もう集団で遊ぶことが楽しくなってきます。
人見知りの時期が過ぎる1才半ごろより、少しずつ小さな集団の中に子どもを入れてあげることも、豊かな人間関係を育てるために大切なことです。
下の子をいじめる →閉じる
これまで、親の愛情を一身に集めてきた子が下の子が生まれた途端、愛情を奪われた様に思い、赤ちゃんがえりをしたり下の子をいじめたりします。「お兄ちゃんでしょ?」と叱ったり、我慢させるのではなく「あら、赤ちゃんがうんちしたみたいね。一緒におむつを替えてあげようね。」「おむつもってきてくれるかな?」などと、うまく誘って一緒に育てていっているという気持ちを持たせましょう。そして、手伝ってくれたことをうんとほめましょう。時には赤ちゃんが寝た時などには、たっぷりだっこして「だいすきよ」とメッセージを届けてあげましょう。
他の子に乱暴する →閉じる
乱暴な子は、欲求不満のサインを出しているのです。充分に話を聞き、たっぷりふれ合い、思いを受け止めましょう。たっぷり愛されているという思いを持てば、少しずつおだやかな子になっていきます。乱暴な子は、家庭全部で子どもへの接し方や家族全体の雰囲気をふりかえってみなければなりません。親が子どもの気持ちを受け止めず、感情に任せてたたいたり、叱ったりを繰り返していると子どもは無気力になるか、乱暴になるかのどちらかです。
強情・反抗 →閉じる
「強情な子・反抗的な子」と大人が思う子は、(だれも分かってくれない、どうせ)と心にガードをしている状態です。大人が強く言えば言うほど、ガードが固くなり、てこでも動かなくなってしまいます。ゆっくり向き合って、「○○ちゃんがこんなことされたら、どんな気持ち?」「○○したら、こうなるのでは?どうしたらいいと思う?」と、周囲の人の気持ちや困ることを話してあげましょう。ゆっくりと話し合い、気持ちを理解し共感できると子どもの心はとけていきます。気持ちを理解することは、甘やかしではありません。
嘘つき →閉じる
子どもの嘘には、2通りあります。空想の世界を楽しんで現実との区別がつかなくなり、「きのう空を飛んだよ。」とか「きのう大きなケーキ、お父さん買ってきたんだよ。」というようなかわいい嘘。大人や友達の注目を浴びたくて嘘をつく時もあります。
もう1つは、失敗の許されないしつけの厳しすぎる環境にあって、自分を守るためにつく嘘です。
かわいい嘘は、「そうだったらいいね!」と聞いていっしょに楽しんであげればいいのですが、叱られるからつく嘘は、考えなければいけません。
大人に愛され認められている子、大人の愛情が信じられる子は、嘘をついてもすぐに「嘘でしょ?」と言えば「そうなの、ごめんなさい。」とあやまることができます。
「自分は、失敗・あやまちを認め、励まして行く大人であるか」子どもの嘘に悩んでいる人は、自分自身を振り返ってみましょう。
泣き虫 →閉じる
言葉の十分でない子が泣いて自分の要求を訴えるのは、あたりまえのことです。赤ちゃんは、泣いて不快・空腹・不安を訴えます。2才をすぎても、いつも泣いて訴える子は、泣かないと聞いてもらえないか、又は、泣けば必ず聞いてもらえる体験をしたか、どちらかではないでしょうか?泣き終わるのを待って、じっくりと話を聞きましょう。
一方、色々なことにすぐ泣く子は感受性の鋭い子ですから、良い事として受け止めることも大切です。「そう、悲しかったんだね。」「なるほどね。」と気持ちを共感し合えると、素敵ですね。
こわがり →閉じる
こわがりの子は想像力が豊かであったり、危険が予測できたりという能力の豊かな賢い子が多いのです。「こわくないよ」「こわがりだねえ」などとなじるのでなく、「そうだねえ」「心配なんだね」と気持ちを受け止めてあげましょう。こわくてトイレへ行けないような子には、手をつないで一緒に行くことでスキンシップにもなり、そのうち行けるようになります。
赤ちゃんの人見知りや、お母さんの後追いをするのは正常な発達をとげている証拠です。
指しゃぶり・爪かみ →閉じる
指しゃぶり・爪かみは子どもがそうすることによって、気持ちを安定させている癖の1つです。大人になって指をしゃぶったり、爪をかんでいる人はまずいませんから、そのままにしておいて大丈夫です。
ただし、爪は短く切っておきましょう。外で友達と元気に遊びまわることが楽しくなると、指しゃぶりも爪かみも少なくなってきます。
性器いじり →閉じる
小さい子どもの性器いじりは、性的な関心があってするのではなく、手持ち無沙汰な時に気を紛らわせる手段とみるべきです。叱るより、他のことに気持ちを向けさせ、遊びに誘ってやりましょう。
おもちゃのひとり占め →閉じる
3才未満児がおもちゃをひとり占めにするのは、成長の証です。とったりとられたりしてけんかになったり、泣いたり泣かせたりして学んでいきます。こうしたことを繰り返して、ゆずり合ったり、分けあったりして遊ぶ方が楽しいということが分かってきます。
まだまだ、ひとり占めする2才児には、「貸してちょうだい。」「いいですよ。」と、動作に伴う言葉を教え、貸し借りを遊びに取り入れるようにしていきましょう。
盗み →閉じる
社会のルールを知らない子が、「欲しかったから。」と言ってスーパーのガムやあめをいつのまにか勝手に手にして食べていたりして、親が慌てる事があります。「まだ、分からないから。」と一度許すと、とんでもないことになります。小さくても「ダメな事はダメ。」ときちんと教えましょう。そして大人と一緒にあやまりに行きましょう。
盗みは、最初に発見した時の対応が肝心です。
わがまま →閉じる
自己主張とわがままは、紙一重です。親の言いなりにならず、成長の1つとして喜ぶべきことです。
しかし、スーパーなどで、ひっくりかえって泣きわめいてわがままを通そうとしたり、思い通りにならないと泣いて暴れるというような時は、喜んでばかりいられません。
興奮がおさまるのを待って、ダメな理由、人への迷惑、社会のルールなどをゆっくり言い聞かせましょう。
いじめられる →閉じる
家庭で大事にされすぎて、何でも大人にやってもらっていた子は、集団の中で受け身になる事が多く、反発できず、いじめられているように見えます。又実際強い子がちょっかいをかけて反応を楽しむ対象にもされてしまいがちです。しかし受け身になって強い子の言いなりに動いているように見える子が、実際は強い子へのあこがれをもって楽しんで従っている場合もあります。弱い子、いじめられやすい子、人の言いなりになりやすい子は、その子の持っている良さをみんなの前で大いにほめ、自信を持たせ、友だちにも認めてもらえるように工夫しましょう。
左きき →閉じる
赤ちゃんの脳はまだ完成していませんから、脳とつながる手の働きも右手、左手という風に利き腕がはっきりしていません。それどころか手と同時に足も動いたりしています。脳が発達するにつれ、きき腕がはっきりしてくる、という側面もありますが、逆に、きき腕をはっきりさせることで脳も多面的に発達する、ということもあります。一般に左脳は右手と結びつき、言語・計算・論理の脳と言われ、右脳は左手と結びつき、創造・感覚の脳と言われます。だから文字や計算などは、できれば右手でさせる方がよい、という説もあります。又、日本の文字は右手で書く方が書きやすくできています。
いずれにせよ、チックやおねしょなどの身体状況を押してまできき腕をなおす必要はありませんが、就学を前に、ぜひ右ききになおしたいと思われる方は、箸やスプーンを持ち始めた頃から、意図的に右手に持たせるようにしていくべきでしょう。子どもへの負担が少なくてすみます。はさみ・描画などは左ききでしたら、なおす必要はまったくありません。
人をける・たたく →閉じる
人をたたいたり、蹴ったりしておもしろがるような時はきちんとした関わりが必要です。「よくないことだ」ということを目を見てきちんと伝えましょう。その上で、欲求不満やストレスの発散と受け止め、抱しめたり、スキンシップを十分にとり、じっくりと関わります。
家で上の子や父母にいじめられたり、体罰を受けている子が集団の場で、たたいたり、蹴ったりして気持ちを発散させるということもあります。
いずれにせよ、乱暴な子は心が満たされていない状態です。周囲は愛情をたっぷりと伝える方法を探らなければなりません。
人をかむ →閉じる
6、7カ月の頃の赤ちゃんは歯の生え始めの時期で、確かめるために、お母さんの手や腕にかみつくということがよくあります。自我の芽生える2才頃の集団の中では、かみつきが多くなります。おもちゃの取り合い、保育士の膝の取り合い、時には特に理由もないのに目の前にいたというだけでかみついてしまうこともあります。
かんだ時には、その都度、「貸してって言おうね」「ごめんって言おうね」と声をかけ、友達とつながる言葉、仲良くなれる言葉を教えていきます。
そして、楽しい遊びの工夫をして、子どもたちのイライラの解消に努め、噛む状況を作らないようにしていきます。
また、家庭で母親にたっぷりだっこされ、愛情をいっぱいもらっている子は、噛むということが少ないのも事実です。
母から離れられない →閉じる
赤ちゃんがお母さんから離れられないのは当然のことで、正常な発達です。少しづつ周囲のことに興味を持つようになり、離れられるようになります。たとえ、朝、泣いてお母さんと別れても、すぐに泣き止んで、保育園では楽しく遊び、お母さんがお迎えに来ると、飛びついていくということになります。
いくつになってもお母さんから離れられない子は、下の子が生まれたために、余計にしがみつくようになった場合、お母さんに十分だっこしてもらっていない場合などが考えられます。
お家でうんとかわいがられ、たっぷりだっこしてもらっている子は、集団の中にも早く元気に入っていけるようになります。
自閉的傾向 →閉じる
3、4才になっても極端に1つのことにこだわって、周囲の言うことを受け入れられない場合、言われたことに対し、うまく言葉のキャッチボールができなかったり、おうむ返しが多かったり、自分の言いたいことを一方的に話し続けるだけであったりする場合は、自閉的傾向を疑ってみなければいけません。集団の中での子どもの様子をよく観察し、専門機関へ相談しましょう。
やる気がない →閉じる
子どもは正常に育っていれば、何事にも好奇心いっぱいで、新しいことにどんどん挑戦していきます。子どもがやる気を出さない原因は、◆大人の過保護・過干渉のため、要求が子どもから出る前に手を出している
◆いつも否定されていて、自分に自信がない
◆かわいがられたり、受け入れてもらっていない
◆体調が悪い
◆能力よりあまりに高い課題でやる気がおこらない
などです。子どもが失敗するのは当り前です。失敗を許し、やろうとした意欲を多いに認めていくようにすれば少しづつやる気が出て来ます。
1つの遊びしかしない →閉じる
大人から見るといつも同じ遊びをしているようでも、子どもの遊びは少しづつ変化しているものです。たっぷり遊んで満足したり、飽きれば、子どもは次の遊びに移っていきます。しかし、大人の誘いや友人の誘いにもまったく興味を示さなかったり、何ケ月も遊びに何の変化も見られない子や、ちょっとルールが変わるとパニックになったり、こだわりが強いように思える場合は生活・性格・生育歴を総合的にふり返ってみる必要があります。その上でも原因がわからなかったら、専門機関へ相談しましょう。
テレビばかりみている →閉じる
テレビは知識を広め、楽しみを与えてくれる便利なものですが、受け身の情報がすべてですから、どんなに長時間見ていても、現実の社会を生きていく力とはなりません。むしろ害が大きいのが今のテレビ界かもしれません。やはり、テレビに関しては何らかの制限が必要です。テレビについて家中が話し合い、決めることが大切です。◆まず、大人が、見たい番組だけを選んで見る。あとは消すという習慣を身につけましょう。
◆食事の時間は消しましょう。
◆子どもが見ている番組は、大人も一緒に見て話し合いましょう。
低俗な番組を見ている場合は、頭ごなしに叱るのではなく、一緒に見て、大人の思いを伝えていけば、子どもも番組を多面的に見ることができるようになります。
子どもにチャンネル権をあずけっぱなし、見せっぱなし、テレビにおもりをさせっぱなしということがないようにしましょう。そのためにもテレビは一家に一台がいいですね。
登園・登校をしぶる →閉じる
何もかも満たされた快適な家庭生活が保証されている今の日本において、その家庭を離れ、規律や我慢の多い集団生活に入っていくことは、子供たちにとって、多かれ少なかれ大変なストレスです。そのストレスをうまく乗り越えて成長していけるかどうかは、それまでの育ちと入っていく集団の質に大きくかかわってきます。担任と相談し、問題のありかを探りましょう。幼児の場合、朝お母さんと離れるのがいやでぐずっていても、すぐに気持ちが変わり、元気に遊ぶことが多いのです。あまり深刻にうけ止めず、担任に様子をよく聞きましょう。
また、家でたっぷりと抱っこされたりして愛情をもらっていない子は、かえって分離不安に陥り、よけい登園・登校をしぶるということもあります。育ちをふり返るチャンスかもしれません。
集団の質に問題がある場合は、親は全力をあげて子どもを守らねばなりません
動作がおそい →閉じる
子どもの時間の流れは大人と比べ、うらやましいくらいゆったりとしています。だから靴をはくのも、脱ぐのも、大人よりずっと時間がかかります。ちょっと深呼吸して待ちましょう。どうしても我慢できない時は靴の片方をはかせてあげたり、洋服の袖を半分通してあげましょう。また、注意散漫で遅くなってしまう子には、「着がえたらこのおやつ食べようね」などと、次への期待を持たせましょう。
5才になっても、まだまだ注意散漫な子は、時計を見て行動することや、自分で決めることをさせ、うまくできたらうんと認めていきましょう。
食事時に注意散漫になりやすい子には、「次に席を立ったらお片づけしようね」と約束し、本当に片づけさせましょう。
落ち着きがない →閉じる
子どもは、いつも活発に動き回っているのが普通で、大人から見れば、元気な子は常に落着きがありません。心配した方がよいのは3才をすぎても興味が次々と移り、1つのものに集中して遊べない場合です。このような時には、小さい時に1人遊びをたっぷりさせたか、1人遊びをしている時に余計なかかわりをして遊びを中断させることが多くなかったか、振り返ってみなければなりません。
3才を過ぎても、どんな遊びにもあまり関心を示さず、友達や大人の周囲にいることが多い場合は、児童相談所などに相談してみましょう。
だきぐせ →閉じる
だき癖は癖というより、その子の育ちに必要な要求であると受け止めましょう。だっこをたっぷりしてもらった子は、自分が愛されているという自信にあふれています。そして人を好きになり、いろんなことに自信を持って取り組む子になります。
できるだけたっぷりとだっこしてあげましょう。そのための時間がとれる様、周囲は家事などに協力しなければなりません。たっぷりだっこされて心が満たされれば、子どもは膝をはなれて遊びに出かけます。
乳児で、いつもと様子が違い、だっこしても泣き止まない時は、腸閉塞などの急性の疾患がないか、虫さされ、湿疹などがないか、耳や鼻に異物が入ってないか、空腹でないか、のどがかわいていないかなど、よく確めましょう。
けんか →閉じる
子どもの育ちにけんかは必要ですし、つきものです。兄弟げんか、友達とのけんか、いずれもけんかすることにより、子どもは相手にも思いがあること、自分の思い通りにならないことがあることを知り、どうしたら仲良く遊べるか、方法を学びます。大人は子どもがけんかをしていると何がなんでもすぐやめさせたり、「仲介」と称して一方的に、どちらかを「悪い」と決め付け、あやまらせておしまいにしがちです。そしてますます関係をこじらせます。
子どもがけんかした時は、まず、たたく、けるなど、手足が出ることになったら、離します。気持ちが落ち着くのを待って、それぞれの気持ちをじっくりと聞き、良い悪いの判断を混ぜないでそれぞれの思いを相手に伝える橋渡しの役をします。その後、乱暴した理由の良し悪しは別にして、きちんとあやまらせます。
気持ちを伝えたところで「どうしたらいい?」と両方に尋ね、仲直りの方法を子どもに考えさせるようにします。周囲の子にも、意見を求めるのもよい方法です。
けんかは必ずといっていいほど、両方ともに言い分があるものですが、どうしても片方の子だけに非がある時は2人きりになってじっくりと話し合いましょう。
友達と遊べない →閉じる
3才をすぎても、まだ友達と遊ぶことができない子は、一人遊びを十分させたかふりかえってみましょう。たっぷりと一人遊びをし、自分の世界が持てている子はやがて友達と遊ぶことにも新鮮な喜びを見出していけます。そのためにも、一人で遊んでいたらその世界をそっと認めてやり、見守っていくことが大切です。3才をすぎてもまだうまく遊べない場合は、大人が遊びに誘ったり、仲立ちをして、友達とつながっていく言葉「ありがとう」「ごめん」「貸して」などを、時と場合に応じて使っていくことを教え、遊びのルールを教え守らせていくように導きましょう。